これまでの連載では、システム管理者に求められる5つの基礎的能力を論じ、こうした能力を獲得する秘訣、自己研鑽の方法や好ましいシステム管理者の人材育成などを論じてきた。
今回は、若干逆説的な論旨を展開してみようと思う。自ら努力しても良い人材を獲得して育成しても辞めてしまう人材が看過できないまでに増えてきているからである。
バケツの穴を塞がないまま「人材が来ない。採用コストが。せっかく育成したのに、」と宣う管理者(システム管理者と言うより組織管理者・マネージャーになどに見られる状況かもしれない。)
- 目次
- 1. クリエイティブな人材は画一的・標準的に存在するものか?
- 2.1日で社員に去られる職場「絶対に忘れるな、守れ」が多すぎる!
- 3. 1日で社員に去られる職場「不文律」が多すぎる!
- 4.クリエイティブ人材に逃げられない職場を作ろう。
- 5.5S・カイゼンもストレスの少ない職場づくりに効果!
- 6.最後に 現代の若者に対応する難しさ。
1.クリエイティブな人材は画一的・標準的に存在するものか?
本連載では優れたシステム管理者に求められる能力とは、(1)創造力(2)計画力・実現力(3)生産性・収益性を高める能力(4)継続力(5)顧客視点と総括している。
https://www.sysadmingroup.jp/kh/p26113/
こうした能力を高いレベルでバランスした状態で保有し、何処の組織でもチカラを発揮できる人材は、そこらあたりに転がっているわけではない。しかも、クリエイティブな人材とは一芸に長けたいわゆる尖った人材であることが多いのではないか?
多くのプロジェクトマネジメントや組織を論じる書籍・記事の類はそうした尖った人材を定着させる「間違ったトリセツ」を提供してしまっていると感じる。
で、今回、そうした「間違ったトリセツ」に替えるべき「正しいトリセツ」を提供してみようと思う。
スタイルとしては反面教師である。次項以下に例示したような職場・組織管理になっていないか?自分ごととして、また組織的にチェックすることを強くお薦めする。これまでDX支援を行なってきた優良企業では、こうしたところは皆無であるが、それでも、「こんなに人事制度を充実して、サポートも尽くし、とことん面倒見良い会社で社風も明るいのに。(超短期で辞めた社員が出る)」などと嘆く例が少なからず見られるからである
2.1日で社員に去られる職場「絶対に忘れるな、守れ」が多すぎる!
こういう職場は、エンジニア、スタッフから見ると、むしろ即辞めるべき会社である。
諸注意の中で「絶対に○○しないこと」「絶対に○○を忘れないように」と絶対的義務付けを言ってくる職場。
「なんだ。新職場じゃ厳しく言わないと。あたりまえ」と思う管理者・監督者は自らのマネジメントを反省した方が良い。
これがなぜいけないか。
絶対に守れないからである。新人が初日からノーミスで済むはずがないと考えるべきだが、初日から絶対に守らないといけないことがあると言うことは、初日からなんのフォローも指導もなく、ダブルチェックもシステム的制度的リカバーもなく、新規スタッフひとりの絶対の注意力のみに義務なり禁止が委ねられていると理解しないといけない。(多少気付けばフォローしてくれるかも知れないが後出しの注意になりがちである)
そして絶対事項を守れないなら、絶対に怒られる。
例を挙げる。(エンジニアではないが。)地元スーパーでの観察では、毎日アルバイトに任されている冷蔵庫の温度チェック欄が空欄になっているところがある。冷蔵庫の温度計をメモってハンコ押すだけなのだが、これはDXが普及しつつある今では、計測機器による自動記録と、監督者のダッシュボード画面での確認が望ましいであろう。手遅れにならない時点でアラートも出せる。
ところが定時にチェックする仕組みになってないから、必ず漏れが出て後追いで2日分、悪くすれば1週間分叱咤されることになる。そこで罵倒されても凹むだけで改善もしなければ、定時にチェックできてないのだから、意味がない。食品衛生法などで決められているのだろうが、大丈夫か?冷蔵庫、壊れないか。
「バイトテロになるからSNSへの酷い画像アップは絶対にやめること」だったらまだしも、「絶対に」を多用するだけの監督者が、理由や社会的影響、自分へどう跳ね返ってくるか?などを丁寧に説明するだろうか?絶対的注意義務をエンジニアに押し付け(DXで良くある間違い、「入力作業をスタッフ個人に移し、総務グループの負担を半分に削減しました!と言うのと同じ。)業務・責任の「転嫁」である。すぐやめよう。
3.1日で社員に去られる職場「不文律」が多すぎる!
新規採用のアルバイターなどが初日に直面する躓き。その大半が不文律、である。
最初は何もわからないのは当たり前。慣れていれば当たり前でも慣れてないうちは、初日はすべてが新体験である。慣れているはずがない。
高度な業務を行うITエンジニアでもあり得る。業務で当然に出入りする施設の開錠の方法、すぐ利用する社内システムのログインIDとアドレスなど。出勤初日、はりきって早く会社に着いた!もう鍵の開け方がワカラナイ。採用時の説明は、大抵次のようなもの。「あんなあ、着いたら多分先輩が来ているから、挨拶して、カードスリットしてね。」カギの開け方は聴いてないしどこにも書いてないやん(そら、鍵の開け方を入口のそばタレに書いておいたら泥棒さん入り放題だけど。)こう言うのは不文律とは言わない、単に説明不足ではないか?との反論も聞こえてきそうだが、物理的な入退室管理は、マネジメント上最低限のセキュリティであり、本当に重大な事案に発展する可能性もあるので、敢えて不文律と表現しておく。
暑い時期に書いているので、多少世俗的な話題も一つ。
今度は別のサービス業の現場である。炎天下でなくても最近は業務中に、水分を補給する「給水ルール」などにも配慮されるようになっている。が明文の規定をわかるように張り出している職場はまだまだ少ないようだ。冷蔵庫が休憩スペースにあり、自販機も設置してあり、ドリンクを摂れるようになっていたりするが、さて喉が乾いた。控え室に入るのはサボリと言われないか?ではポケットにPETボトルを突っ込んでおいて飲むしかないな。飲む。
「ピピーッ!(笛までは吹かないだろうが)お客さまの前で飲み食いするな。おまけにポケットが膨らんでみっともない。接客業をなんと心得る!」と叱責される。「その腕時計とスマホバックもダメでしょ。白衣の下にモノを持たない。」
次から次へとこのようなどうでも良さそうなことが出てくるのがこの手の職場である。
日本の産業・組織の悪いところは不文律の存在である。書いてないのに守らないといけない。これ、欧米・諸外国ではありえないことである。マニュアル化されていてマニュアルに書いてないと守られない。想像もつかないことをされかねない。欧米のブルーカラー・ホワイトカラーが分化した社会、契約社会の常識であり、最近では多言語対応が必要で、マニュアルが写真やイラストになっていることも多い。が、作業ができるレベルに詳述されている。日本の中小製造業でも進んだところはそこまで配慮している。
細かいことを言うようだが、基本に戻って考えて欲しい。不文律でよし、としていると言うことは、経験値や感覚、作業手順を文書化すらできていないと言うことでしょ。DX・リーンマネジメントの1番地、観察(Look・See)から課題を拾い出す、カイゼンする、ここで手順化、明文化、記録が必須になるのだが、若手エンジニアにも嫌われるこうした職場はDXのスタート地点にも立てていないのだと、認識するべきであろう。
4.クリエイティブ人材に逃げられない職場を作ろう。
一般的に知的な作業を担うスタッフが集う職場とは、どんなものであろうか。主にマネジメント面で考えてみる。フリーアクセスやパーテーションレスなどハード面は置いておく。バーナードの組織の三要素がまず思い浮かぶが(組織の要件で検索するとTOPに上がってくると言う意味でも)、1)コミュニケーション、2)貢献意欲、3)共通目的の3つが挙げられる。国家の要件のように、領土、国民、主権と言うのとは様相が違うがこの質問を投げかけると、社長(経営者)、従業員、社是・社訓、などを返してくる経営者も少なくないだろう。
原点に還って考えてみると、そのような考えは少し形式的にすぎないだろうか?
1)コミュニケーション
組織とは二人以上の構成員があるため、必然的にコミュニケーションが発生し、円滑に進まねばならないが、前掲の「絶対に」はコミュニケーションを拒否する言葉でもある。「不文律」は絶対的規律の存在を前提として、上の立場のものが自由に変えられるマジックカードであり、これもコミュニケーションを断つ威力は絶大である。
管理的な立場と従う立場、職能上の役割分担はあっても、コミュニケーションは対等な立場を前提としないと成立しない。
上位下達、唯我独尊、俺についてこい、的なコミュニケーションはバラバラな組織よりなお悪く、無理矢理秩序ある外見を保てたところで遠からず崩壊に向かうであろう。
必要な解は、社長から全ての従業員、サプライヤーや顧客まで人間的に対等なコミュニケーションの実現をめざすことである。
より具体的には、遵守が必要なキマリの明文化、手順化、数値化、不文律が残っていれば、明文に落とし込んで、必要なキマリなのか、不要で形式的なものなのか吟味して改善していく。
そして、「絶対に」と言う言葉も撲滅したい。人間の、スタッフの基礎的注意力「だけ」に頼る注意義務は極力減らしていく。
これだけでも、相当スタッフへのプレッシャーや叱責を受けることによる意欲減衰が相当避けられるのではないか?
2)貢献意欲
1)で築いた良好なコミュニケーション、これだけでも、スタッフの意欲はアップするが、これだけでは組織貢献の視点が欠けている。チームや仲間意識社長から顧客まで関係者は全員対等なパートナー、との意識づけを緩やかに浸透させることによって、みんなが自分ごととして自分の職責を全うし、「オレはしんどいのイヤ。辞めたい。あと?知らんけど。」といった風潮をなくしていく。気をつけないといけないのは、このプロセスを強圧的に、あるいはスケジュールガチガチのプロジェクトマネジメントみたいな手法で進めないこと。そんなことをすると、窮屈さが見え透いてしまい、逆にみんなやめていく。
3)共通目的
ちょうどDXの時代である。単に、長時間労働も厭わず、売上を増やそう、みたいな前時代的なスローガンでは誰もついてこない。ここで、大きく発想の転換が必要だ。
就業規則や前述のキマリの明文化、絶対的注意義務のみによって維持される秩序やコストや数量を最優先する思考などは一旦ゼロにして考えてみたい。
特に目標としたい価値観はより少ない量、労働力、速度で、より高い付加価値を産もうとの考え方である。服装、服務、挨拶などの立ち居振る舞いまで、細部や形式についてスタッフに義務を課している職場、企業のなんと多いことか?接客機会が少ないコーディングのスタッフなら、スーツも要らないし、Tシャツ短パンの方がリラックスして効率が上がるかもしれない。来客があると直接業務に関係のない同室者にまで立ち上がって「いらっしゃいませ」の礼を求める会社が良い会社のように思われがちだが、一度電話応対で中断した集中力は20分かけないと元に戻らないとも聞く。
効率が上がらないならやめよう。代わりにそれぞれ、笑顔や真剣な面持ちを見せれば、顧客にも信頼されると思うのだが、いかがだろう。
コストや数量優先も単位労働あたり労働生産性を損なう。品質や安全は大切だが、スピードは相反しかねない要素である。ゆったりと、気をつけて、安全で快適なものを時間をかけて制作していくのが今風である。手づくり産品を手がける企業がDXで成功しているのはこの発想の転換があるからである。
5.5S・カイゼンもストレスの少ない職場づくりに効果!
そのかわり、効率アップに繋がる5S・カイゼン※は、エンジニアリング部門でも総務部門でも、徹底的にやろう。例に出した食品スーパーなど、物流分野、建設分野などでも実は、製造業では当たり前の5S・カイゼンが浸透していない。
事務部門でも、書類ケースや文房具、コピー用紙を運ぶカートなど、テーピングで良いので、置く場所を決めていこう。探す手間、衝突によるけが、すれ違い時の余計な時間などが節約できて、ストレスフリーになっていく。
※「スーパーバックヤードには飲料のケースを詰んだカゴ台車がいっぱいで通路を塞いでいたりする。白線もひいてなければ、パネルトラックの駐車位置すら、区画されてなかったりもする。」をカット、と同じ意味です。
6.最後に 現代の若者に対応する難しさ。
最初に「こんなに人事制度を充実して、サポートも尽くし、とことん面倒見良い会社で社風も明るいのに。(超短期で辞めた社員が出る)」などと嘆くとある優良中小企業の例をあげた。
この、辞めた社員はなぜ数日でやめていったのか?わからない。が、30代のフリーターを続けるひとに話を聞いた時にふと気づいた。このひとは、「かまわれたくなかったのではないか?」と言うことである。

図3 手取り足取り、の指導。今では身体的接触はタブーとなる。
普通には、いろんな新人スタッフに対するサポート制度があって、社長、管理者、先輩とのコミュニケーションも確保されていて、チャットやSNSツールも自由に使えたりするのは良いこと、と思われる。が、IT技術者の中には、クリエイティブな能力を持った人間でも、「変」なヤツも居るわけである。
平均的に同じようなペルソナを思い描き、対応しても万人に受け入れられる時代ではなくなっていて、さあ、「変」なヤツだから要らない、とも言えない。
どの社員にも公平に。全従業同じ環境と処遇と服装で、など従前の常識は続けにくくなってくるだろう。DXそのものがパーソナルサービスに大きく傾斜していく中で、働く個人個人のニーズにあわせてパーソナライズされた業務を担当してもらう、より難しい組織運営を求められる時代がもう、ほら、そこまで来ている。
※5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
整理は使わないものを捨てること。整頓は捨てるものは捨てた上で置く場所を決めること。清掃は置いといて清潔は以上の3Sの状態を維持すること。しつけは礼儀の話でなく、5Sを習慣づけずっと5S活動を継続すること。
連載一覧
筆者紹介

ITコンサルティング DXpower 代表
◆独立行政法人中小企業基盤整備機構機構 中小企業アドバイザー
◆公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 コーディネータ
◆一般社団法人エコビジネス推進協会事務局長
◆BAC 大阪
◆みせるばやお

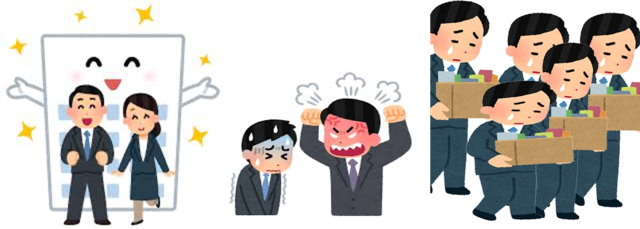

コメント
投稿にはログインしてください